欧州工作機械国際見本市見学番外編(2)
大きな駅前広場に着いた頃は、辺りは明るくなっていた。大勢の通勤客や大きなバックをもった旅行者が駅構内を足早に行き来していた。駅の中を見物しているとアラブ系の中年女性に道を聞かれ、私も分からないと返事を返した。地元の人間に間違えてくれたことは、私が地元に溶け込むことを工夫をしていたからだと思う。
このミラノ駅は映画「アンタチャブル」(主演;ケビン・コスナー、ショーン・コスナー)のクライマックスシーンであるシカゴ駅階段での銃撃戦の撮影をした場所。ずいぶん前にこの映画を観たあと、10年ほど前だと思うが、トリノにあるお客様を訪問後、トリノ駅からミラノ駅まで急行列車で移動した。その時雑誌で当時のシカゴ駅の風情を残しているのはミラノ駅であるとの記事を思い出し、駅に到着したあと撮影した階段を見にいき、映画のシーンと重ね合わせて思い出していた。なにしろ私はこの映画が好きで3回も観ていた。
結局ホテルに帰るのに2時間もかかってしまった。次の日は再度ドゥーモ行きのコースを設定しなおし、道に迷いながらも45分で到着。帰りは迷わず走ってきたので30分でホテルに着いた。朝もっと明るければ、これほど迷わないのだが、まだ陽が上らないうちに走っている人は皆無で、6時ごろになるとジョギングしている人に数人会うようになった。
 ミラノからの帰路。モナコに宿泊したとき、私はF1レース(モンテカルロ)のコースを走るため、ホテルでコースが載っている地図をもらい夜のうちに準備をした。朝5時日が昇っていない街は暗く、なかなか地図の通りに走ることが出来なかった。というのは私が想像していたより道路の幅があまりにも狭く、こんな道路でF1が走ることが出来ないと思った。そこで海岸沿いにスタート地点に行き、コースを確認しながら走っていた。だんだん明るくなって回りの景色が良く見えるようになると、間違いなくF1コースだった。
ミラノからの帰路。モナコに宿泊したとき、私はF1レース(モンテカルロ)のコースを走るため、ホテルでコースが載っている地図をもらい夜のうちに準備をした。朝5時日が昇っていない街は暗く、なかなか地図の通りに走ることが出来なかった。というのは私が想像していたより道路の幅があまりにも狭く、こんな道路でF1が走ることが出来ないと思った。そこで海岸沿いにスタート地点に行き、コースを確認しながら走っていた。だんだん明るくなって回りの景色が良く見えるようになると、間違いなくF1コースだった。
一周約2.3km。道幅は一般道路と同じ幅で、路面も同じ、モンテカルロホテル前のヘアピンカーブはすごかった。こんなカーブを100㎞超のスピードで突っ込んでくる。「すごい」の一言に尽きます。
10年の間にヨーロッパ出張の度に、宿泊先の街をジョギングしてきた。思い返すと最初に走ったウィーンでは迷子になって1時間の予定が2時間半。ドイツのハノーバーは空港脇のホテルで、何もない真っ暗な道を。プラハの街は街全体が世界遺産に登録されていてすばらしい景観。そのほかドュッセルドルフ・バース・バーミンガム・プリマス・アムステルダム・ストックホルムの街を走ってきた。街を車で行くより、その国の様子が分かる。私が走る5時頃清掃員が道の清掃やごみの収集をしている。ほとんどがその国の人ではない人達だ。国の経済格差が朝の清掃員の人達を見ると分かるような気がする。6時頃になると朝食の準備をするレストランの様子など、その国の食の情報を見ることが出来た。
欧州工作機械国際見本市見学番外編(1)
オークマ欧州工作機械国際見本市(通称EMO)のもう一つの楽しみは、朝早く起きて市街地をジョギングすることである。おおよそ10kmを1時間から1時間半かけて、初めての街を走ることは車やバスから見る風景とは、まるで違う街の生活を見ることが出来る。またヨーロッパの出張では時差ボケで午前4時頃眼が覚めてしまう。部屋で横になっているよりも、朝の散歩やジョギングで体を動かしたほうが、はるかに体調が良いものである。
ミラノ中央駅から徒歩15分に位置するウェスチンホテルに到着すると、すぐフロントで地図を貰い、翌朝のジョギングコースを調べる。朝4時に目を覚まし、事前に用意したウェアーを着込み、ジョギングシューズを履いた。準備運動はロビーで行ったが、ロビーには誰もいなく、フロントの人が物珍しそうに見ていた。ホテルを出ると暗く信号機の光やビルの広告ネオンで道路が判別出来るだけであった。ホテルの玄関前にはタクシーが5~6台待機していたが、運転手は客がいないのか車から出て数人がタバコをふかしながら、談笑していた。一瞬私のほうを見たが、客でないことがわかると無視するようにおしゃべりを始めた。
私は地図を見易いように、また必要な場所が表になるように、細かく折りたたみポケットに入れた。道に迷ったとき、長い時間もたもたして地図を見ていると、観光客とさとられ被害にあわないとも限らない。地元の人間になりきることがリスクを軽減するコツである。気温は15~16度、半袖のTシャツにジョギングシューズ、ゴルフの帽子をかぶり、ホテルの名刺と地図、それに20ユーロをポケットに入れ走り始めた。20ユーロは最悪道に迷って帰れなくなったとき、タクシーを捕まえホテルまで帰るためである。
最初に計画したコースはホテルを中心に右回りで、観光名所のドゥーモと隣接する教会に行って帰る予定でした。最初は外国の見知らぬ街を走る昂揚感もあり、体は軽く感じられ、頭に入れたコースを快調にミラノの街を走り続けた。しかし広い通りは十字路だが、少し狭くなった通りはロータリーになっていて、ロータリーを中心に放射状に道が幾つもあり、非常に道が分かりにくい。一本道を間違え、次のロータリーで間違えると方向感覚が狂ってしまう。走り初めて40分様子がおかしいと思い、地図を見た。自分は地図のこの地点にいるだろうと思い、通りの名前や住所の番地を見たが、該当する地名がなかった。
そこでいくつかの番地と通りの名前を覚えて、走り回って10分。ようやく記憶した通り名が眼に入ってきた。自分のいる場所の位置が分かったので、目的地のドゥーモを諦め、道が分かりやすいミラノ中央駅に向かった。ヨーロッパの都市部でのジョギングは、道が間違いやすいことは何度も体験していた。迷子になったのも初めてではなく、何度か体験していたので慌てることはなかった。

『ドォーモ』
欧州工作機械国際見本市見学記
オークマ欧州工作機械国際見本市(通称EMOショー)を10月5日(月)から10月12日の日程で、オークマ㈱の森専務を団長に17名の視察団に参加した。我々製造業は製品を作り出す道具である工作機械の動向を注視し、常に先端の機械・システムを追及することは大事なことと考えている。EMOショーは日本国際工作機械見本市(通称JIMTF)と米国シカゴショーの三大工作機械見本市の一つで、2年に 1回開かれている。ドイツのハノーバー市の開催が中心で2回続けた後にパリ市で開催、またハノーバー市に戻り2回開催した後、ミラノ市で開催される。つまり12年間のサイクルでハノーバー⇒ハノーバー⇒パリ⇒ハノーバー⇒ハノーバー⇒ミラノの順で行われる。近年このサイクルを見直ししてハノーバー市に固定化されるようだ。
 ミラノ市郊外の会場はハノーバーよりも一回り小さい感じであるが、建物はシャレた作りと色彩が眼を引いた。入り口には各国の言葉で、日本は「ものつくり魂」、アメリカは「THE KNOW HOW」、中国は「制作能力」等、製造業の理念が書かれたポスターが眼に入った。最初にオークマさんのブースを訪問し、花木社長・オークマヨーロッパの青山副社長の歓迎を受けた。展示機械の説明を聞いた後、私は主に共和工機の増田副社長と一緒に順路を決めて、会場の展示機械の傾向を話し合いながら、丹念に見て回った。
ミラノ市郊外の会場はハノーバーよりも一回り小さい感じであるが、建物はシャレた作りと色彩が眼を引いた。入り口には各国の言葉で、日本は「ものつくり魂」、アメリカは「THE KNOW HOW」、中国は「制作能力」等、製造業の理念が書かれたポスターが眼に入った。最初にオークマさんのブースを訪問し、花木社長・オークマヨーロッパの青山副社長の歓迎を受けた。展示機械の説明を聞いた後、私は主に共和工機の増田副社長と一緒に順路を決めて、会場の展示機械の傾向を話し合いながら、丹念に見て回った。
展示されている機械は原子力発電設備のタービンのハウジングやシャフトを加工する大型の複合NC旋盤・五面加工機・M/Cが多く展示されていた。新興国向けのインフラ整備関連をターゲットに売り込みを図る意図が十分に読み取れる。我々の仕事の建設機械向け油圧機器は中国を初めとする新興国のインフラ整備に直結するので、中期的な展望は期待出来そうだ。来年に向けての予測が確信に変わるひそかな期待感が生まれた。オークマの方に質問すると、私の感想と同じ世界各国の工作機械メーカは、日米欧よりもBRICsを初めとする新興国のインフラ整備関連の分野の回復が期待されるとのことでした。
2年前のEMOは中国メーカの多さとインドメーカのマシニングセンター、ブラジルメーカのマザーマシンと云われる門形マシニングセンター、ロシアメーカが眼を引いた。私はその時不覚にもインドやブラジルでNC工作機械が生産できるのか想像もしていなかったので、大変驚いた。今回も中国は数多くのメーカが出展し、韓国・台湾も頑張っていた。確実に新興国BRICsが工作機械の市場で存在感を増してきたように思う。一方日本は5大工作機械メーカのうち2社が出展を取りやめ、出展会社数が20年前に較べると激減しているのが印象的でした。日本の存在が、失われた15年の停滞で確実に薄くなっていくのを複雑な思いで今回の視察会で感じていました。
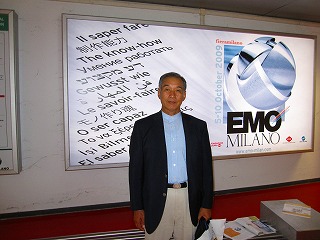
5S・TPM改善発表会
9月30日(水)朝8時40分から午後3時15分まで、22チームによって5S・TPM改善発表会が行われた。発表は現場の活動板の前で1チーム10分 ①分科会名・チーム名②チームメンバーの構成とチームリーダ・発表者名③活動エリア④改善の目的・目標⑤活動の実施状況⑥活動の成果⑦個別改善事例の紹介⑧反省と次回に向けての抱負の順に報告が行われ、審査員は私を含め4名でその場で採点を付けていき、その合計点の平均値で優劣を競うようにした。
 私は30年程前にお客様のQCサークル発表会に出席し、サークルメンバーが皆で改善活動をする様子を聞き衝撃を受けたのを、今でも鮮明に覚えています。当時は従業員が少ないこともあって、改善は私と顧問の二人で行っていたので、従業員が皆で改善をするということが奇跡に思え、協立でも取り入れようと試みました。しかし様々な試みをしたが、定着は難しかった。挫折しては再度始めるということを繰り返していました。失敗した原因は推進体制にありました。当時従業員は20名位ですから事務局は私が務めました。しかし私は工場の営業・製造・生産技術・生産管理・品質管理・総務・経理を一人で務めていましたので、どこかの部門が忙しくなるとフォローが出来なくなり、改善の時期が過ぎてから報告をさせようとすると「やっていません。連絡がないからやめたと思った。忙しい。」等々やらなかった理由を並べ立てていました。再度仕切りなおしをすると品質問題でお客様に報告、新規の仕事の打合せ、新規の仕事の設備投資・レイアウト・見積などが続くと又もとに戻ってしまうという連続でした。
私は30年程前にお客様のQCサークル発表会に出席し、サークルメンバーが皆で改善活動をする様子を聞き衝撃を受けたのを、今でも鮮明に覚えています。当時は従業員が少ないこともあって、改善は私と顧問の二人で行っていたので、従業員が皆で改善をするということが奇跡に思え、協立でも取り入れようと試みました。しかし様々な試みをしたが、定着は難しかった。挫折しては再度始めるということを繰り返していました。失敗した原因は推進体制にありました。当時従業員は20名位ですから事務局は私が務めました。しかし私は工場の営業・製造・生産技術・生産管理・品質管理・総務・経理を一人で務めていましたので、どこかの部門が忙しくなるとフォローが出来なくなり、改善の時期が過ぎてから報告をさせようとすると「やっていません。連絡がないからやめたと思った。忙しい。」等々やらなかった理由を並べ立てていました。再度仕切りなおしをすると品質問題でお客様に報告、新規の仕事の打合せ、新規の仕事の設備投資・レイアウト・見積などが続くと又もとに戻ってしまうという連続でした。
 あれから30年、2007年9月14日に5S・TPM改善活動のキックオフを宣言し、5Sを中心に改善活動を始めました。推進体制は本部長が私、副本部長が広瀬工場長、事務局が佐々木工場長付で6ブロック24チームの組織体を作りました。3ヶ月に1回、成果の発表会を行い、優秀チームには報奨金を授与しました。
あれから30年、2007年9月14日に5S・TPM改善活動のキックオフを宣言し、5Sを中心に改善活動を始めました。推進体制は本部長が私、副本部長が広瀬工場長、事務局が佐々木工場長付で6ブロック24チームの組織体を作りました。3ヶ月に1回、成果の発表会を行い、優秀チームには報奨金を授与しました。
 5Sが一定のレベルに達したので、2009年6月にTPM活動に移行することを決め、9月30日が最初の発表会になりました。22チームの報告は未熟なところが多くあったが、私が30年前に奇跡に思えた、皆で改善活動を進めていることに胸が熱くなりました。30年掛かってようやく始まることが出来た。さーこれからだ。
5Sが一定のレベルに達したので、2009年6月にTPM活動に移行することを決め、9月30日が最初の発表会になりました。22チームの報告は未熟なところが多くあったが、私が30年前に奇跡に思えた、皆で改善活動を進めていることに胸が熱くなりました。30年掛かってようやく始まることが出来た。さーこれからだ。
改善発表の優秀チームと優秀分科会長の写真を掲載して、労に報いたい。
最優秀賞 品質保全分科会 特攻隊Aチーム 桝井リーダー
準優秀賞 品質保全分科会 エキス・マキナチーム 大木リーダー
準優秀賞 5S分科会 出荷係チーム 篠崎リーダー
努力賞 品質保全分科会 TEAM-Uチーム 窪田リーダー
努力賞 品質保全分科会 増渕チーム 増渕リーダー
努力賞 計画保全分科会 ブラックムラーノチーム 藤田リーダー
最優秀分科会長賞 品質保全分科会 高橋課長代理
準優秀分科会長賞 計画保全分科会 清水課長代理
おめでとう。
経営者協会県西地区支部役員会
9月25日(金)茨城県筑西市のホテル新東において、県西地区支部役員会が開かれました。
役員会は支部長、副支部長3名、幹事長、副幹事長、幹事9名の計15名で構成され、支部長は㈱スミハツの若山さん(常務取締役管理本部長)、副支部長が私と樋口さん(NC東日本コンクリート工業㈱社長)・中川さん(日立化成工業㈱下館事業部長)が、幹事長は杉山さん(関彰商事㈱人事部長)が務めています。事務局は社団法人茨城県経営者協会の清水専務理事、加藤部長、生井課長、後藤主事の4人です。
支部活動報告では、立山所長(ココロジー経営研究所)による「環境で強い会社をつくる」の講演会の評価・反省が行われ、続いて下期事業の検討が行われた。下期事業の講演会は「新型インフルエンザ対策」、企業見学会ではエコドライブの体験学習を行うことにした。エコトレーニングを受けたドライバー(事務局)の年間データを年間走行距離・CO2排出量・CO2吸収に必要な木の本数そして燃料費の4項目について、通常運転とエコドライブの比較をマトリクスにして見やすくし、燃料費では 約30%近くの改善が見られた。非常に興味深い提案だった。
支部総会・行政懇談会についての検討の後、役員・幹事の交代について、長い間、幹事長の職で活躍されていた杉山さんが、関彰商事殿の人事異動に伴って、後任の方と交代するとの報告が有りました。その後懇親会が行われました。異業種の方たちとの交流会は大変興味深く、楽しく、勉強になることが多かった。
杉山さんご苦労様でした。
業務連絡会
我々の会社は毎月協力会社に対して業務連絡会を開いて、社長挨拶・受注情報・品質情報・納期遵守率の報告会を行っている。出席会社はきょうわ会(17社)と主要お取引様3社を加えた20社である。きょうわ会は二十数年前に結成し、現三代目会長は㈱木城製作所社長の木城弘明氏が就任している。
9月23日木曜日15時10分から連絡会を始め、私が挨拶でリーマンショックから1年お互いに大変苦労してきたが、ようやく仕事が戻ってきた。しかし、最盛期の50%であることを考えると、慎重に事業の再構築を進めて行きたいと報告した。続いて工場長が受注状況を、購買部長が品質・コスト・納期全般の改善状況を、品質保証部長が品質状況の報告を行い、質疑応答に移った。フクミツプレシジョン㈱福田社長から年初に頂いた表彰式の写真を頂きたい旨の発言があり、購買部長が写真を送ることを約束した。忘れていたとはいえ大変失礼なことしました。他に谷津製作所殿・筑波野口殿・早川機工殿が表彰を受けましたので、同時に贈ることにした。ブログに写真を載せ、お詫びに代えさせていただきたい。
フクミツプレシジョン殿
谷津製作所殿
筑波野口殿
早川機工殿
業務連絡会
宇宙エレベーター③
0.000004%の挑戦
千葉県船橋市にある日本大学二和校地の2009年8月8日は晴天だった。
宇宙ステーションの代わりに、バルーンが上空150mの高さまで上げられ、車のシートベルトがテザーとしてぶら下げられた。 グラウンドの端では、参加8チームが簡易テントの下で着々と準備を進めていた。参戦したのは、日本大学理工学部から2チーム、神奈川大学工学部から2チーム、名古屋大学工学部、静岡大学工学部、ミュンヘン工科大学(ドイツ)、個人参加の「チーム奥澤」の8チームだ。
いずれも手弁当で、自ら旋盤を削りつくり出したクライマーたちは、スーパーマーケットの買い物かごに入りそうな大きさである。競技のルールは、制限時間内での、上昇速度とほかの評価項目で競う。が、単なる記録競争ではない。各テントでは、自チームのクライマーの特徴をパネルで展示していた。このアイデアは、青木教授の提案による。互いのアイデアで、刺激し合い、さらなる技術開発を進めるという、この競技会の大きな目的はここにある。
風にテザーがなびく。ねじれるテザーにはばまれて、クライマーが止まる。初日の午後は、強風で、テスト昇降に切り替えざるを得なかった。各チーム寝ずの最終調整でのぞんだ2日目も晴天。
青木は、ストップウォッチを片手に、記念すべき第一回の競技を見守った。 机上の理論や、コンピュータ内の計算では起こらない、現実が次々と起こる。北米以外で初めての大会とはいえ、賑やかな観客席などない。自分たちが製作したクライマーを、真剣に見上げ、歓声を上げる研究者たちは、何も知らない通行人から見れば、新種のラジコンで遊んでいるように見えたかもしれない。
優勝は、2005年から開発を進め、150メートルまで上げられる実験をできると滞日4日間という強行スケジュールで来日したドイツ、ミュンヘン工科大学チームだった。このチームは、2007年米国で記録された秒速2メートルの速度を打ち破り、150メートルを52秒で上った。
3万6000キロからすれば、150メートルはわずか0.000004%に過ぎない。「初日にあんなに高く見えた150メートルが、もうわけなく見えてくる。来年300メートルにしても、難なくクリアできるかもしれない。いつの日か、何だ3万6000キロなんて大したことないじゃないかと」
「アホなこと」がやがて天空に届く
機械系エンジニアの使命は、どんなに小さく粗末なものでも、理論を形にして作り上げ、見せることだと青木は言う。 「アホなこと」と自嘲気味に微笑みつつも、小さくとも一歩ずつ進む。ゼロからは何も生まれないが、150メートルの実績の種は、やがて芽を出し、天空に届く大樹となるだろう。
「もし明日、世界がなくなるとしても、何か作り続けているって素晴らしいじゃないですか。それが世界の崩壊を防ぐかもしれない」
これまでも、これからも、未来はこうして作られる。
(文中敬称略)
画像をクリックすると動画をご覧いただけます。(WMV形式)
クエスト~探求者たち~
WOWOW 毎週日曜 午前10:00~
宇宙エレベーターで宇宙へ! 青木義男教授の挑戦
9月6日(日)午前10:00
再放送 9月19日(土)午前9:00
この記事を読んで私は出身校ということもあって、大変誇らしく嬉しくなりました。私が学生の時、精密機械工学科の航空研究室で人力飛行機の開発を行っていて、8の字飛行の世界記録を目標に頑張っていたのが思い返されます。私は青木教授の 「この卒業研究には、正しい答えはない。答のない問題の答を探そう」の言葉が大好きです。私達の仕事もこれで良いと云う答えはありません。ある時期うまくいったとしても環境が変わったりすると、ダメになる。過去に成功したから未来も成功体験のままで良い等と言うことはありません。これで良いなどと云う答えはないのです。人生もこれで良いなどという答えはありません。答えのない人生の答えを探して進んで生きましょう。
宇宙エレベーター②
「蜘蛛の糸」のイメージで宇宙へ
エレベーターといっても、我々が一般的に考える建物の中に設置されたものとは違う。イメージとしては、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」のように、天空から垂らされた糸を伝って昇る姿を想像した方が近い。では、どうやって糸を垂らすか。 大ざっぱに言えば、人工衛星から垂らすのである。
地球を回る人工衛星は、地球の重力で内側に引っ張られる。が、遠心力で外側に飛び出す力と釣り合うことで、高度を維持して地球の周りを回転し続けている。これまで世界で打ち上げられた人工衛星は6000個以上、現在も3000個が旋回中だ(JAXAホームページより)。
これらの人工衛星のうち、赤道上の高度約3万6000キロを回る人工衛星は、周期が地球の自転と同じで、地上から見れば相対的に静止して見えるので「静止衛星」と呼ばれる。ここから地上に向け、頑丈なテザー(ワイヤーやリボン状の紐)を垂らす。
テザーの重さで衛星が落ちてしまわないように、地球と反対側にも同じだけテザーを伸ばすと、衛星はバランスを維持し続けながら地球を回る。これをモノレールの線路のようにして昇降機(クライマー)を宇宙に向かって走らせるというのが、宇宙エレベーターのおおよその原理だ。
この構想は、約50年前に既に発表されている。しかし、技術上、実現は困難とされてきた。特に、地上に垂らすテザーの強度は、計算上鋼鉄の180倍が必要だ。
ところが、1991年日本のNEC筑波研究所(当時)の飯島澄男が発見したカーボンナノチューブという新素材が、その条件に見合い一気に宇宙エレベーターの実現への難路に光が見えてきた。
米国の航空宇宙局(NASA)は、2000年、宇宙エレベーターの実現可能性を探り始め、「十分な軽さと強さを持つ材料が開発されれば、建設可能」という結果を得た。2005年から、その技術を探るため、宇宙エレベーター競技会も開催されている。
そして北米以外で初めて、第一回宇宙エレベーター技術競技会(主催・社団法人宇宙エレベーター協会)が、2009年8月、千葉県で開催された。その審判席に青木教授の熱い視線があった。
守りから攻めへの転換点
青木教授が「宇宙」に取り組んで、まだ1年数カ月しかたっていない。 学者としての業績の第一歩は、強化プラスティックに関する研究だった。1981年、25歳の青木は、強化プラスティック協会論文賞を受賞する。マンションなどの共同住宅の屋上に設置された、円筒形のFRP(繊維強化プラスティック)水槽に関する論文だった。
順風満帆に学者への道を目指してきたわけではなかった。
「オフレコにしたいけれど、高校時代は、2度も停学処分を受けたような生徒だった。修学旅行にも参加できず、自宅で反省文を書かされて(苦笑)」 「失った信頼を取り戻すのには、その何倍もの努力が必要になる」。その言葉通り、青木は、人の3倍努力することを心がけてきた。そのためには、無駄なことはさけ、馬鹿なことをいう暇も惜しんできた。
「けれど、そろそろアホなこともやっていいかな」第一の理由は、大学の人間として、つまり後進の研究者を育てるという視点に立てば、一心不乱に研究データを積み重ねるだけでは、いけないのではないかという思いだった。
宇宙へ行く? そんなのできっこない
ここ数年、青木にとってつらい事故が立て続けに起こった。エレベーターの事故や、ジェットコースターの事故だ。直接かかわっているわけではないが、構造力学や複合材料力学、最適構造設計などをフィールドにし、10年以上エレベーターも研究する学者として、新聞社などからコメントを求められた。そんな日々を経て、偶然、宇宙エレベーター協会の講演会に足を運んだのが、2008年4月のことだった。「地上のエレベーターの研究だって大変なのに、宇宙へ行く? そんなのできっこない」
それが、最初の実感だ。
しかし、できないことをそれで片付けてよいのか。自分の目が黒いうちに実現する可能性は限りなく低い。だから放棄するのか...。 たとえ世界が明日終わるとしても、未来を見ている。それが、自分にとっても学生にとっても必要な姿である。青木研究室に、宇宙エレベーターのクライマー開発というテーマが加わった。実験機の製作は大学院生が担当する。卒業研究テーマでも「宇宙エレベーター」が選ばれた。
「この卒業研究には、正しい答えはない。答のない問題の答を探そう」
宇宙エレベーター①
9月4日(金)の記事で、酒井 香代(さかい かよ)氏による「世界ブランドの日本人を追え クエスト 探求者たち」と題して、世界を舞台に活躍し、世界を相手に勝負を挑む日本人たち・・・。中には、日本では無名であっても、欧米各国で唯一無二の存在として名を知られる日本人もいる。
その記事から私が眼にしたのは「宇宙エレベーター」だ。興味を引いたのは1~2ヶ月前、どのメディアか忘れたが、宇宙に行く新しい方法で人工衛星からワイヤーをたらしてエレベーターの要領で、宇宙ステーションに接続するという記事だった。そんな時、日経ビジネスラインの記事を見て驚いたのは、宇宙エレベーターの開発を行っているのは日本大学理工学部精密機械工学科の青木義男教授だということだ。 私は、昭和47年に同学科を卒業し、今でも年に一回程度訪問しているが、話題になっていないのか話しには出なかった。そのような訳でこの記事を紹介したい。
ただの夢じゃない「宇宙エレベーター」
「地球は青かった」という言葉で知られるユーリー・ガガーリンによって世界初の宇宙旅行が実現し、半世紀近くの歳月が流れた。この夏は、宇宙開発機構(JAXA)の若田光一宇宙飛行士が4ヶ月半にも及ぶ宇宙滞在を果たし無事帰還したニュースも記憶に新しい。今や、世界では宇宙は、新しいビジネス市場として注目され、商業的な宇宙旅行の販売も始まっている。
SFの世界の"乗り物"が現実に
2009年7月現在、地上100キロメートル以上の宇宙空間を体験した人は、地球を回る軌道に入らない弾道飛行(準軌道飛行)を含めれば、500人を超えているという。これらの500人強の人が利用した乗り物は、もちろん、ロケットである。
エレベーターで宇宙に行こう。
そう言われて、あっけにとられないのは、世界でもごく少数の人間に限られるだろう。SF作家 アーサー・C・クラークの著作『楽園の泉』にも、宇宙エレベーターは登場する。クラークは、スタンリー・キューブリックが映画化した『2001年宇宙の旅』の作家であると紹介した方が、SFファン以外にはわかりやすいかもしれない。 しかし、この夢のような話は、もはやフィクションから現実へと向かって着々と進行しているのだ。日本で宇宙エレベーターに取り組む中心人物のひとりが、日本大学理工学部の青木義男教授だ。「アホなことを。そう人は言うかもしれない。でもアホなことも大切」と、青木教授はつぶやく。
リーマンショックから1年・・・
米国の大手証券会社リーマンブラザーズが破綻したのは1年前の9月15日。我々の会社は急成長の上り坂を全速力で駆け上がっていましたが、15日に断崖絶壁から真っ逆さまに落ちてしまった。
私が異変を感じたのは、北京オリンピックが行われていた8月でした。上海協立の張総経理から、顧客である上海の日系油圧機器メーカーからの受注が「半減した」との報告を受けました。当初、オリンピック期間中は電力の制限や夏の暑さで生産を落としているとの認識でした。また上海協立は10月に既存の工場より1.5倍広い 工場に移転する計画で、お客様のラインに迷惑をかけないため、作りだめをしている最中でしたこともあって、あまり気にしていませんでした。
しかし、9月に入っても受注は半減。油圧機器メーカーの顧客である建機メーカーがラインを止めて生産調整をしているようだとの情報が入りました。私は疑問に思い中国の状況を調べている時に、リーマンブラザーズ破綻のニュースを聞き、大変なことになったと思いました。
我々の会社はおよそ5年間で売上規模を3.5倍にしました。大きな設備投資を行った結果、損益分岐点売上高が高くなっていましたので、受注が落ちると赤字転落するという恐怖感をいつも持っていました。9月下旬、一部のお客様から生産計画の下方修正の連絡があったのをきっかけに、私は経営幹部を集めて協議しました。そして10月初めに幹部を集め、世界同時不況の波に襲われて経営が苦境に陥ってしまうことを説明し、同時にあらゆる具体的な対策を示し実行していきました。
工場は3班2直4勤2休体制(24時間・30日稼働)を1班1直5勤2休体制に切り替え残業規制も始め、固定費削減・変動費削減を強力に進めることにしました。我々の協力会社に対して月1回行われている業務連絡会においても、大不況に入ることの状況説明を行い、また購買部を通じて協力会以外の取引先にも説明しました。
1年前を振り返ると早く対策を実行したおかげで、最小限の被害で乗り越えてきたと自負していますが、世界同時不況の底はあまりにも深く、協立製作所の財務は大きな傷を負ってしまった。
7月下旬ころから中国の内需拡大策の効果が出てきたのと、お客様の在庫調整が進んで来たので、需要数と生産数が一致すると期待していました。ようやく9月から受注が回復してきました。下半期は受注回復が期待できますが、最盛期の50%~60%であることから少しも気の抜けない状況が続くと思います。それでも我々は今週をもって一時帰休をやめ、21日から一直の正常稼働に戻すことにしました。
我々はこの間、生産管理のシステム改革、5S・TPM改善活動を進め、仕事を組織的に仕組みで出来るように全員で注力してきました。今こそ受注が回復したこのとき、地道に改善活動を行ってきた成果を挙げようと思っています。この成果が確実にもぎ取れるように皆で頑張って行きたい。
私は会社を守るため3ヶ月間で派遣社員130名を契約に従って、解約しました。マスコミは雇い止めと称して大々的なキャンペーンを展開し、企業に対する攻撃を仕掛けてきました。政治家もこれに同調しました。私はこのような社会現象を見て不思議な感じを持ちました。なぜ派遣会社でなく派遣先企業を攻撃するのか。なぜマスコミは法律遵守している企業まで攻撃非難するのか。なぜ派遣社員を雇用している派遣会社を取り上げないで、派遣先の企業を攻撃するのか。なぜ赤字に転落する企業に雇用を守れというのか。経常利益は現金ではないとなぜ言わないのか。利益が出ているのになぜ企業は短期資金を調達できないで、資金繰りに奔走するのか。なぜ派遣法を作った時セーフティーネットの法律を作らなかったのか。等々多くの疑問を持っていました。
私は世界同時不況を受けて、体力差はあるものの企業が乗り越えるには、あまりにもハードルが高いと思う。雇い止めの現象をみてマスコミは、派遣社員に対するセーフティーネットをおろそかにした政治、そして自らの政治に対するチェック機能の甘さを認識すべきと思う。マスコミが対応するべきことは、企業を攻撃するのではなく、国が本来行うセーフティーネットをおろそかにしたことを問題視し、与野党で法案を作らせるように世論を喚起することが彼らの役割だと思う。そして企業に対しては頑張れとエールを送ることが、日本の再生につながると思う。企業は富を生み出すが永遠ではないのだから。









